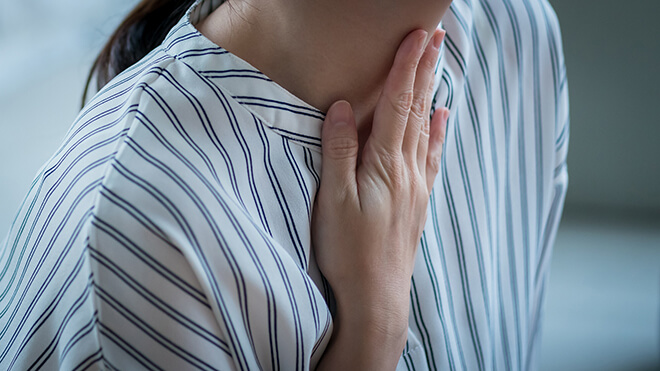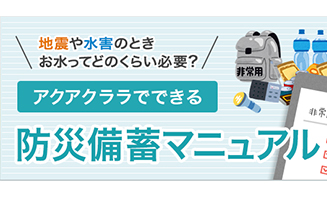医師監修|水を飲み過ぎると太るってホント?「水中毒」の原因と解消法

目次
水太りは、水の飲み過ぎというより、塩分や体調不良で、起こることが多い症状です。成人1人あたり、1日に必要な水分摂取量は1~2Lと言われていますが、運動量や食事内容、環境、季節によっても異なります。排尿・排便の回数や体調をチェックしながら、正しく水分を補給して、水太りしないよう意識してみてください。
宅配水初!「医師の確認済み商品」に認定されました
AskDoctors評価サービスにおいて、内科医100名のうち96%の医師がアクアクララを「ぜひ勧めたい」「勧めたい」と回答。「医師の確認済み商品」に認定されました。
※2023年5月 内科医100名 AskDoctors調べ
https://www.aquaclara.co.jp/askdoctors/
水太りとは何か?

水太りとは、新陳代謝が低下することで体内に水分がたまる傾向となり、顔や手足がむくんだり、トイレの回数が4回以下に減ったり、尿量が少なくなるなどの兆候が現れる症状のことです。
水太りと言えば、水の飲み過ぎが原因と思う方も多いかもしれませんが、通常であれば尿や汗などとして不要な水は体外に出され、それだけで水太りを引き起こすことはほとんどありません。水太りとは、体内で不要になった老廃物を体外に排出させるための「新陳代謝」が低下し、全身の血液循環が悪化している状態を言います。
水太りするとどうなる?
水太りの状態が続くと、体温や血圧を調整する自律神経系の働きも鈍り、さらに新陳代謝を低下させる悪循環に陥るようになります。そのため、水太りでは以下のような症状が見られます。
- 体重の増加
- 尿量の減少
- 下腹部や足、顔のむくみ
- 関節痛
- 自律神経の乱れ
- 肩こり
- 手足の冷え
- 新陳代謝の低下
- 疲労感
- 食欲不振
- 顔色が悪くなる
水太りは、脂肪ではなく体内の水分が増えている状態です。しかし、水太りによって起こるむくみを放置すると、リンパ管から脂肪酸が流出し、脂肪細胞を大きくしてしまいます。すると、脂肪による肥満へと繋がることがあります。
水太りの原因

水太りは、新陳代謝の悪化や血液循環の悪化を伴う症状のため、こうした症状を引き起こす原因が、水太りの原因と言えます。ここでは、代表的な水太りの原因をご紹介していきましょう。
生活習慣
生活習慣には、食事の内容や日々の運動量、睡眠の質などが含まれます。たとえば、塩分の多い食事が習慣化していると、体は水分をため込んで体内の塩分濃度を薄めようとするため、水分がなかなか排出されません。結果的に、体内の水の循環、血液循環、新陳代謝などが悪化します。
加えて、運動不足や睡眠不足も水太りの原因になるため注意が必要です。運動不足は筋肉量の減少とともに、血液循環も悪化させます。睡眠不足は自律神経の乱れから心肺機能の低下を招き、リンパの流れや血行の悪化から水太りの症状を引き起こすため、注意が必要です。
リンパ浮腫
リンパ浮腫とは、何らかの原因によってリンパの流れが滞り、リンパが腫れるように膨らんだ状態です。リンパ浮腫の症状は、リンパの流れが滞っている場所のむくみや、だるさ、皮膚が硬くなる、圧痕(押すと皮膚がへこむ)などがあります。リンパは体内の水分循環において大きな役割を果たしているため、この流れが滞ると、水太りの症状も現れやすくなるというわけです。
参照:
腎臓障害
腎臓は、「糸球体」という毛細血管の毛玉のようなもので血液中の老廃物や塩分をふるいにかけて綺麗にする、体内のろ過装置です。糸球体は、ろ過された原尿に残っている様々なミネラルを再吸収してから、残された水分を尿として排出するという役割も持っています。そのため、腎臓機能の働きが悪くなると、正常な尿排出ができなくなり、水太りの症状を引き起こします。
循環器系障害
循環器系障害とは、心臓や血管などの循環器が正常に働かなくなる病気のことです。心臓はポンプのような役割をしており、血液循環に欠かせません。そのため、心臓の機能が弱くなることは、体の血液循環の悪化に直結し、水太りの原因になります。
水太りの解消法

むくみやだるさといった、水太りと思われる症状が体に現れた場合は、どのように対処すれば良いのか、原因別にご紹介します。
生活習慣が原因の場合
水太りを引き起こす新陳代謝の低下は、腎機能の低下や甲状腺機能異常など明らかな病気の症状がある場合を除き、基本的な生活習慣の乱れが主な原因として挙げられます。中でも乱れた食生活は、新陳代謝機能に悪影響を与えやすいと考えられています。
特に塩分の摂り過ぎは要注意です。味付けの濃い食事やレトルト食品、スナック菓子など、塩分を多く含むものばかり食べていると、体が水分をため込みやすくなり、新陳代謝が阻害されてしまいます。これは塩分濃度が急激に高まった血液を薄めようと、一時的に大量の水分を必要としている状態であり、水分が血管を圧迫すると老廃物の排出までも滞りがちとなってしまうのです。塩分の摂り過ぎが続くと、塩味に対する感覚が鈍くなるのも問題です。自然と濃い味を好むようになり、水太りだけではなく、高血圧症や心臓病、脳卒中発症のリスクを高めることが知られています。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書によると、毎日の食事に欠かせない塩分の1日の摂取量は、成人男性9g、成人女性7.5g以下が適正とされています。塩分の排出を促すカリウムを多く含む食品や利尿作用のあるお茶と一緒に摂るよう心掛けましょう。
リンパ浮腫が原因の場合
リンパ浮腫による水太りの場合は、適度な運動やリンパドレナージ(皮膚をこすってリンパ液を流すこと)によって、リンパの流れを改善させることができます。ただし、リンパ浮腫がⅢ期(皮膚組織が繊維化して硬くなっている状態)まで進んだ場合は、セルフケアのみでの改善が難しくなってしまいます。
自身の状態や適切なセルフケアを行うためにも、痛みや違和感があれば、医療機関を受診してください。加えて、リンパ浮腫の状態にある皮膚は乾燥しやすいため、保湿クリームを使ったスキンケアも行うと良いでしょう。
腎臓障害が原因の場合
腎臓機能の低下は、自覚症状が出にくいため、定期健診などで異常がないかどうかを検査しておくことが大切です。腎臓機能の低下が見られる場合は、食事の面で「減塩」「たんぱく質の摂取制限」「適正なエネルギー量の摂取」などが必要になります。腎機能の程度により、制限の度合いは異なります。
また、適度な有酸素運動や筋力トレーニングも、腎機能の低下を遅らせる対策として有効です。ただし、どの程度の対策や治療が必要になるかは、医師の指示を仰ぐ必要があります。
循環器系障害が原因の場合
循環器系障害も、年齢に関わりなく誰もが発症する可能性があり、自覚症状がないことも少なくありません。基本的には、医療機関の検査と、医師の指示に従うことが必要です。
循環器系障害を予防するためには、適度な運動や、栄養バランスの良い食事、禁煙や飲酒量のコントロールなどが有効になります。可能な距離であれば、徒歩や階段を使うことや、食事に野菜を増やすこと、週に2日は休肝日を設けるなどが有効的です。
参照:
適度な運動と食事を見直し水太りリスクを低下させよう
通常、体内にたまった余分な水分や老廃物は、全身を張り巡る「リンパ管」を経由して体外に排出されます。他の血管は、心臓が動いている限り自動的に血液が循環されていきますが、リンパ管の場合は、筋肉を動かさなければ循環が止まってしまいます。
デスクワークの時間が続くなど、運動不足の状態が続きリンパ管の働きが滞れば、水太りの状態がなかなか解消されません。リンパ管は、皮膚のすぐ下を通っていますので、こまめに体を動かし、皮膚や筋肉を定期的に伸び縮みさせる(ストレッチ)ことが、水太りの予防・解消に繋がります。
寝る前に食べ過ぎたわけでもないのに、翌朝に体重を測ったらキロ単位で体重が増えていたら、水太りを起こしているかもしれません。なんとなく足がむくんでいるように感じたり、まぶたが腫れぼったくなったりしていたら要注意です。水太りは悪化すると太りやすい体質になってしまうだけではなく、高血圧症や心臓病などの生活習慣病を引き起こす恐れがあるため、上記を参考に食事を見直すなど早めに対処するようにしましょう。
※本記事で、病気症状についての記載がございますが、ご心配な方は専門機関にご相談されることをおすすめします。
まとめ
水太りの症状は、日々の生活習慣によって引き起こされることが多いため、まずは食事内容の見直しと、適度な運動、水分補給、質の良い睡眠などを心掛けることが大切です。また、水太りの症状が慢性的に見られる場合は、医療機関を受診し、医師の指示のもと、早めの対策をとっていきましょう。
監修者
井上 志穂 (いのうえ しほ)

国立大学医学部卒業後、公立病院にて2年の初期研修を修了。3年目からは癌治療を専門としながら、幅広く内科疾患の診療に従事。治療が必要となる前の生活習慣の改善、また病気についての正しい知識が大事であることを実感し、病気についての執筆活動にもあたっている。