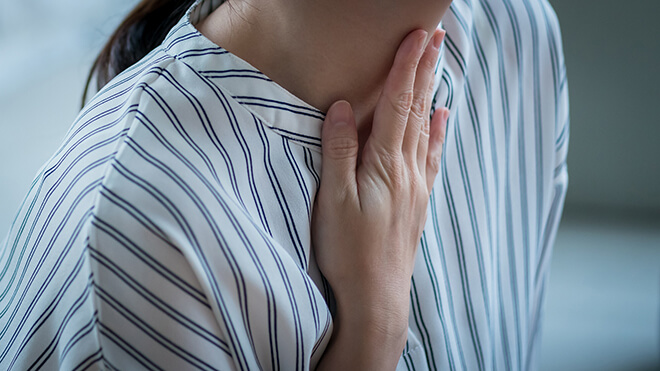医師監修|新生児が汗をかきやすいのはなぜ?赤ちゃんの寝汗や汗対策も解説

目次
寝起きの赤ちゃんを抱っこした際、「衣類とシーツがぐっしょり濡れている」という経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。これにより、寝汗がすごくて赤ちゃんの体調を心配する方もいるでしょう。
そこで今回は、赤ちゃんが汗をかきやすい理由をご紹介します。また、寝汗をかいたら気をつけたいことや、赤ちゃんの寝汗対策もまとめているので、ぜひご参考にしてみてください。
赤ちゃんは汗をかきやすい?その理由とは
「赤ちゃん(子ども)は汗をかきやすい」というイメージがありますが、実は発汗量自体は大人に比べて少ないのが特徴です。発汗量は生まれた直後がもっとも少なく、それから量が増えますが12歳でピークを迎え、あとは減少していきます。では、赤ちゃんは大人に比べて発汗量が少ないのに、なぜ頭からシャワーを浴びたかのように汗をかくのでしょうか。
汗腺密度が高いから
赤ちゃんが汗をびっしょりかく理由は、汗腺密度が高いからです。汗腺とは、汗を作り皮表に分泌する腺のこと。赤ちゃんは密集している汗腺から汗が出るため、汗っかきに見えてしまうのです。
さらに、睡眠中は汗が出やすく、深い眠りについているときほど発汗量が多いといわれています。赤ちゃんは睡眠時間が長いため、その結果、発汗量が多くなり布団が汗で湿ってしまうのです。
体温調節機能が未熟なため
赤ちゃんが汗をかきやすい理由は、体温調節機能が未熟であるためです。大人の場合、体温を下げようと汗をかくだけでなく、自律神経の機能も働きます。そのため、頭からシャワーを浴びたかのようにびしょびしょに汗をかくことはありません。
一方、赤ちゃんの場合、汗をかくことでしか体温を下げられないため、部屋が暑かったり厚着をさせたりすると、密集している汗腺から汗が出て、びっしょりになるといったことが起きます。
暑い環境で過ごしているから
冷房を使用しているとき・寒いときは「赤ちゃんが寒くて風邪をひかないか」と心配になり、厚着をさせたり、布団をたくさんかけたりすることもあるでしょう。また、暑い時期には、「エアコンは赤ちゃんによくないのではないか」と考え、あえて冷房を使用せずに窓・ドアを開けて過ごす方もいます。すると、赤ちゃんが体温を下げようと汗をかいてしまうのです。
このほか、赤ちゃんをベビーカーに乗せて外出をする際、「背もたれ部分が汗でびしょびしょになっていた」という経験をしたことがある方もいるでしょう。
サンシェードがあるから太陽に当たらないし涼しいと思われがちですが、実はアスファルトのほうが気温は高くなります。ベビーカーに乗っている赤ちゃんは地面に近くなるため、熱い空気に包まれます。すると、暑さ対策を施していないベビーカー内は暑くなり、赤ちゃんが汗をかいてしまうのです。
赤ちゃんの寝汗で気をつけたいこと

前述したように、赤ちゃんは睡眠時間が長いためたくさん汗をかきます。赤ちゃんが寝汗をかいたらそのまま放置するのではなく、以下の点に気をつけましょう。
肌トラブル
赤ちゃんの寝汗で気をつけたいことが「肌トラブル」です。汗を放置していると皮膚の中に汗が溜まり、あせもができてしまいます。あせもとは、肌に赤いブツブツができたり、痒みを伴ったりする肌トラブルです。
赤ちゃんが痒くて引っ掻いたり衣類で擦れたりすると悪化するだけでなく、皮膚の免疫力が弱まって細菌に感染すると“とびひ”を起こします。とびひになるとほかの部位にも移ってしまうため、範囲が広くなると治療に時間がかかってしまうだけではなく、ほかの人にも感染します。赤ちゃんが浸かったお風呂の水は流す、同じタオルを使用しないなど、とびひが完全に治るまでは気をつけて生活を送らなければなりません。
このような事態を避けるためにも、あせもを予防することが大切です。あせもができやすい場所は、主に頭や額、脚の付け根、肘の内側、膝の裏側、おむつで覆われている部分などがあげられます。汗が乾きにくくむれやすい部位です。寝汗をかいたらこまめにガーゼで汗を拭き取ったり、着替えたりするのがよいでしょう。できれば寝起きにシャワーで汗を流せれば完璧です。
寝冷え
赤ちゃんが寝汗をかいたら、「寝冷え」にも気をつけなければなりません。汗で洋服が濡れたままの状態で寝かせ続けると、身体が冷えてしまいます。「せっかく寝かしつけたから起こしたくない」と思い、そのままにすると風邪をひいてしまうため放置しないようにしましょう。
外出時には着替えを持参したり、着替えさせやすい前開きタイプの洋服を着用させたりすればスムーズに着替えさせることができます。
また、赤ちゃんが少し汗をかいた状態でタオルケットをかけていないことも寝冷えの原因につながるため、適宜確認をしてかけ直す必要があります。寝冷えを防ぎたいときは、スリーパーの活用がおすすめです。
スリーパーは着る毛布のようなもので、赤ちゃんが動いてもはだけてしまう心配がありません。これにより、寝冷えを防ぐことができます。スリーパーにはノースリーブタイプや長袖タイプなどさまざまな種類があるので、季節に合わせて使い分けましょう。
脱水症
赤ちゃんが寝汗をかいたら、「脱水症」にも気をつけなくてはなりません。繰り返しになりますが、睡眠中は汗が出やすく、深い眠りについているときほど発汗量が多くなります。
そのうえ、赤ちゃんは1日のほとんどを寝て過ごしているため、授乳時間が過剰に空いてしまうと脱水症を引き起こす可能性があるでしょう。生後3カ月ぐらいまでは赤ちゃんが寝ていても授乳時間になったら起こして母乳・ミルクを与えることが大切です。それ以降は、心配しすぎる必要はありませんが、夏場は合間に湯冷ましや赤ちゃん用のお茶などで水分補給することも考えましょう。
なお、赤ちゃんの場合、脱水症になると下記のような症状が見られるため、あわせて覚えておきましょう。
- 泣いても涙が出ない
- 顔色が悪くなる
- 肌がカサカサする
- 舌や口の中が乾いている
- 脈が速くなる
- 手足が冷たくなる
- 尿量が減少する
- 目がくぼんでいる
- 頭(大泉門)がくぼんでいる
すぐに取り入れたい!赤ちゃんの寝汗対策

赤ちゃんが寝汗をかくと、上述したように「肌トラブル」「寝冷え」「脱水症」に気をつけなければなりません。できるだけ寝汗をかないようにするためにも、また、寝汗をかいたときのためにも以下の対策を取り入れるのがおすすめです。
室温を調整する
赤ちゃんが寝汗をよくかく場合は、室内の温度が高いことが考えられます。たとえば夏場に冷房を使用せず、窓・ドアを開けている場合、風の通りが悪いと室内の温度が高くなります。これでは暑くて汗をかいてしまうため、冷房を活用することをおすすめします。
ただし、冷房を使用する際は設定温度を下げすぎてはいけません。また、赤ちゃんに冷房の風が直接当たると体調を崩してしまうので、エアコンの風向きを変えたり風が当たらない位置に赤ちゃんを寝かせたりしましょう。
部屋の端などエアコンの涼しい空気が届きにくい場所に赤ちゃんを寝かせる場合は、扇風機やサーキュレーターを上向きにして首を回しておくのがおすすめです。そうすれば、室内の温度のムラをなくせて過ごしやすい快適な環境を作れます。
寝具・衣類を薄手のものにする
寝具・衣類で寝汗をかく場合は、薄手のものに変えるようにしましょう。冬の時期、赤ちゃんが寒いと思って厚手の毛布をかけたり、厚手素材の衣類を着用させたりすることもあるはず。
しかし、赤ちゃんが汗をかいているのは暑い証拠です。赤ちゃんにスリーパーを着用させ、その上から薄手のブランケットをかけて温度を調整しましょう。
なお、寒くても室内であれば、赤ちゃんに靴下を履かせる必要はありません。赤ちゃんは手足で体温を調整しているため、靴下を履かせると身体に熱がこもって汗をかく場合もあります。赤ちゃんの手足を触ったときに大人が温かいと感じるときは、赤ちゃん自身は「暑い」と感じている場合がほとんどです。普段から赤ちゃんに靴下を履かせている場合は、それが汗をかく要因になっていることも。できるだけ暖かい室内では、履かせないようにしましょう。
汗取りパッド・ガーゼ・タオルを活用する
赤ちゃんの寝汗対策には、汗取りパッド・ガーゼ・タオルを活用するのがおすすめです。汗取りパッドやガーゼを赤ちゃんの素肌と肌着の間に挟んでおけば、汗をかいても着替えさせる必要がありません。汗をかいたタイミングで汗取りパッドやガーゼを抜き取ることで赤ちゃんを起こさずに済み、また肌着が汗で濡れてしまうのも防げます。
このほか、頭の下にはタオルを敷いておくとよいでしょう。頭もたくさんの寝汗をかくので、下にタオルを敷いておけば汗をかいたときに抜き取ることができ、汗で身体が冷えてしまうのを防げます。
ただし、頭の下にタオルを敷く場合は赤ちゃんの顔にかからないよう注意が必要です。タオルが顔にかかっていないか、こまめに確認しましょう。
汗をかいている赤ちゃんへの対応
赤ちゃんがたくさんの汗をかいているようなときは、身体が冷や肌トラブル、脱水症に注意しましょう。びっしょり汗をかいている赤ちゃんへの適切な対応を解説していきます。
やさしく汗を拭き取る
赤ちゃんが汗をかいているようなら、こまめに汗を拭いてあげてください。赤ちゃんの肌はとても敏感なので、やさしく吸い取るように汗を拭きましょう。
乾いた布やガーゼなど、表面が固い布は肌へのダメージになることもあるため、ゴシゴシ拭いてしまわないよう注意してください。少し湿ったおしぼりや、ウェットティッシュなど、やわらかい布もおすすめです。肌にそっとふれて、布で汗を吸い取るように拭いていってください。
水分を与える
赤ちゃんが汗をかいていたら、こまめに水分を与えることが大切です。赤ちゃんはのどが渇いていても、言葉で伝えることが難しいので、大人が定期的に水分補給できるように管理しましょう。乳児の場合、1日に必要な水分量は、体重1kgあたり約150mLです。
外出時に母乳やミルク以外の水分を与えるときは、1回20~30mLに分け、口に含ませるように飲ませましょう。生後6カ月くらいまでは、白湯か赤ちゃん用の麦茶がおすすめです。ミネラルウォーターの場合は、臓器への負担が少ない軟水を与えてください。
夜間に気持ちよさそうに寝ているときでも、脱水症を避けるため、授乳時間になったら起こして母乳やミルクを与えるのが基本です。
とくに暑い時期は夜間でも寝汗をかくため、夜間の授乳は辛い日もあると思いますが、母乳やミルクで、水分補給させてあげましょう。
着替えと沐浴

赤ちゃんの服が汗で濡れているようなら、着替えさせてあげましょう。汗をかくことも赤ちゃんにとっては大切なので、汗をかかないようにするよりも、必要な汗はかいてもらい、汗拭きや水分補給と同時に、着替えもこまめに行ってください。
保育園などでは1日2~3回着替えることも少なくありません。基本的には、衣服で汗を吸って乾燥させつつ、汗を長時間肌に付着させないよう注意してみてください。
加えて、朝と夜に沐浴で汗や老廃物を洗いましょう。低刺激の石けんをよく泡立てて、顔や身体をやさしく泡で包み込むように洗います。沐浴後は乾燥しやすいため、保湿外用薬をまんべんなく肌に塗り、スキンケアを行ってください。
月齢別のおすすめ肌着

赤ちゃんは、汗のかき方や行動が成長とともに変化していくため、赤ちゃんの肌着も月齢に合わせて選んでいきましょう。「0~3カ月頃」は、まだ首がすわっておらず、全身がやわらかいのが特徴。汗を拭いたあと、寝かせたままか着替えられる肌着がおすすめです。着物のように前開き(打合せ)になっている短肌着や長肌着なら、汗も拭きやすく着替えもしやすいでしょう。
「3~4カ月以降」は、手足をバタバタと動かすようになるため、上半身と下半身を分けて留められる「コンビ肌着」がはだけにくくおすすめです。「6~7カ月頃以降」は、おすわりや、ずりばいなど、赤ちゃんの動きが大きくなってくるので、動きやすいボディ肌着(ボディスーツ)に切り替えていきましょう。
買った衣類は「水通し」を忘れずに
赤ちゃんの肌はデリケートです。直接肌にふれたり、口にいれたりしそうな衣類は、買ったあとに一度洗っておく「水通し」をしておきましょう。手洗い表示のあるものは、洗面器などの容器を使い、赤ちゃん用洗濯洗剤を使って洗ってください。水通しをすれば、吸水性もよくなるため、赤ちゃんの汗対策にも有効的です。
水分を与えるならウォーターサーバーがおすすめ

赤ちゃんに水分を与えるなら、ウォーターサーバーの利用がおすすめです。やかんや電気ケトル・電気ポットを使ってミルクを作る場合は、お湯が沸騰するまでに時間がかかるため、赤ちゃんにすぐミルクを与えることができません。
その点、ウォーターサーバーがあればお湯はすでに準備されているので、スピーディーにミルクを作ることができます。
このほか、母乳やミルク以外で水分補給をさせるときもウォーターサーバーが役立ちます。冷たい水を一気に飲ませると嘔吐や下痢が起こる可能性があるので、赤ちゃんには常温の水を与えなければなりません。
ウォーターサーバーがない場合は、冷蔵庫からペットボトルの水を取り出し、一度温める必要があるでしょう。その点、ウォーターサーバーがあれば温水と冷水を混ぜ合わせることで、赤ちゃんが飲める温度の水が作れます。夜中眠くても手軽に適温の水を準備できるので、育児の負担軽減にもつながるでしょう。
まとめ
赤ちゃんは寝ている間にたくさんの汗をかくため、枕やシーツが汗でぐっしょり濡れてしまうことがあります。寝汗を放置していると、「肌トラブル」「寝冷え」「脱水症」を起こしかねません。まずは寝汗をかきにくい環境を整えてあげましょう。
それでも、寝汗をかくことはあると思います。寝汗に気づいたら洋服を着替えさせたり、ガーゼで汗を拭き取ったりしましょう。また、脱水症を予防するために、寝起きの赤ちゃんに水分を与えることが大切です。授乳時間まで時間があり、寝汗がすごいときは脱水症になっていないかもこまめに確認し、部屋の温度や風通しの状態を確認しましょう。
なお、ウォーターサーバーがあればお湯を沸かす必要がないため、ミルク作りが格段に楽になります。水を飲ませたいときも温水・冷水を混ぜれば赤ちゃんが飲める温度の水をスピーディーに作れるので、ミルク作り・適温の水作りの負担を軽減したい方は、この機会にウォーターサーバーの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
※この記事は正しい情報発信を行うために、医師に監修を依頼しております。商品について医師が推薦を行うものではありません。
監修者
江原 和美(小児科医)

保有資格:日本小児科学会 専門医・コンサータ・ビバンセ登録医・イギリス医師免許
イギリスの医学部を卒業後、日本の医師免許を取得。神奈川県内の市中病院にて初期研修および後期研修を終え、埼玉県内の小児病院に勤務。プライベートでは、3児の母として出産・子育てを経験。現在は一般病院やクリニックの小児科外来を担当するほか、小児発達外来や地域の発達支援にも携わっている。