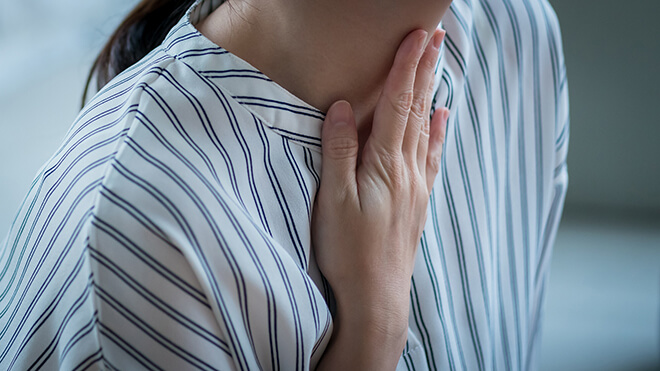医師監修|脱水症予防法8選!脱水症の症状や注意したいシーンも解説

目次
脱水症状を予防するためには、毎日の水分摂取の習慣が重要です。体内の水分が不足すると脱水症を引き起こしやすくなり、最悪な場合は命に関わる危険性もあります。では、脱水症を防ぐには、どのタイミングで水を飲むのがよいのでしょう。
今回は、脱水症の原因や症状をはじめ、注意すべきタイミング、かくれ脱水に気づくためのポイント、予防法をご紹介します。また、脱水症予防におすすめしたい、アクアクララのウォーターサーバーについても解説しているので、ぜひご覧ください。
脱水症を引き起こさない!日常生活で取り入れたい予防法・8選

まず、脱水症を引き起こさないために、日常生活で取り入れたい予防法を4つご紹介します。
こまめに水分補給をする
脱水症を予防するには「こまめな水分補給」が欠かせません。一度にたくさんの水を飲むのではなく、定期的に水分補給しましょう。たとえば、水分が不足しやすい「起床時」「スポーツの前後」「入浴前後」「飲酒後」「就寝前」の水分補給は必須。また、「喉が渇く前」に水分補給をするのもポイントです。
好きな飲み物を飲む
脱水症を予防するには「好きな飲み物を飲む」のも効果的です。とくに、ご高齢の方や小さい子どもの場合、気分によっては水分補給をしないこともあります。それでは予防どころか脱水症を助長してしまうため、好きな飲み物で水分補給を促すようにしましょう。ただし、糖分の多い飲み物に関しては飲み過ぎないよう注意が必要です。
「普段あまり水分をとらない」という大人の方も脱水症を引き起こしやすいので、好きな飲み物を飲んで水分を補うようにしましょう。とはいえ、アルコールやカフェインは避けることが大切です。
アルコールには利尿作用があるため、トイレに行く回数が増え、通常よりも体内の水分が排出されやすくなります。カフェインにもアルコールと同様に利尿作用があるので、水分補給には向いていません。
従って、脱水症を予防するために水分を摂取するなら、好きな飲み物で、かつアルコールやカフェインが含まれていない飲み物をおすすめします。
フルーツやゼリーで水分を補う
脱水症を予防するなら、「フルーツやゼリーで水分を補う」のも一案です。先述したように、とくにご高齢の方や小さい子どもの場合は飲み物をすすめても、気分によっては飲んでくれないことがあります。そのような場合、フルーツやゼリーを食べてもらうとよいでしょう。
フルーツやゼリーには水分が多く含まれているため、おいしく味わいながら水分を補給することができます。ご高齢の方や子どもが好きなフルーツやゼリーを常に用意しておけば、自ら食べて水分を補えるはずです。
部屋を適温に保つ
「部屋を適温に保つこと」も脱水症の予防法のひとつです。電気代の値上がりにより、節約目的で「扇風機やエアコンをつけない」という方もいるでしょう。しかし、温度調整しないのは危険です。
とくに夏場は気温が高く汗をかきやすいので、窓を開けて扇風機を使用したり、冷房をつけたりして室温調整してください。また、日が落ち気温が下がる夜間にも、脱水症を起こす危険性があります。就寝時の室温調整にも十分配慮しましょう。
冬場は、乾燥が原因で脱水症を招く可能性があります。ストーブや暖房は室内をより乾燥させるため、湿度を保つことが大切です。
たとえば、加湿器の使用や濡れタオルを室内で干すなどすると乾燥を防げます。また、霧吹きで水を空気中に噴出させる、容器に水を入れて枕元に置いておくといった方法も乾燥対策になるので、ぜひ試してみてください。
風邪気味のときは無理をしない
風邪気味のときは、微熱や咳が出たり、呼吸が荒くなったりすることで、体内の水分を失いやすい状態になっています。また、下痢や嘔吐の症状があるときも、水分を失いやすいため、警戒が必要です。
質のよい睡眠をとる
寝不足になると脳の働きが鈍くなり、体温調節を上手く行えなくなるため、質のよい睡眠をとることが大切です。とくに、夏場の熱帯夜は汗をたくさんかき、寝不足になる可能性が高いです。就寝前や起床後の水分補給を忘れずに行いましょう。
お酒を控えめにする
アルコールは利尿作用があるほか、アルコールの分解にも多くの水を必要とします。飲めば飲むほど水分を失いやすいため、お酒は控えめにしておきましょう。飲酒時には、飲んだアルコールと同量の水を飲むことがすすめられています。
朝食をしっかりとる
朝食が苦手な方もいますが、朝食で水分や塩分、栄養素をとることが、1日の健康につながります。生野菜サラダやお味噌汁、シリアルなど、水分が多く食べやすいものを朝食にして、一日の活動に必要な栄養をしっかり補給しておきましょう。
水分不足が招く危険な脱水症とは?

ここでは、脱水症のメカニズムや主な原因、症状に加え、熱中症との違いについても解説していきます。小さなお子さんや高齢者が、とくに気をつけたいポイントも紹介します。
脱水症とは
脱水症とは「体内にある体液が不足した状態」です。体液といっても水だけではありません。体液は、ミネラルやタンパク質などで構成されており、これらが不足した状態を脱水症といいます。
脱水症になると、喉の渇きや体のだるさ、立ち眩みといった症状を引き起こすだけでなく、重症化すると意識障害なども引き起こすため、早めの水分補給が大切です。
主な原因
脱水症の原因のひとつに、「水分の摂取量が不足していること」があげられます。とくにご高齢の方は、口渇中枢(こうかつちゅうすう)における感受性が低下し、喉の渇きに気づきにくくなります。水分の摂取量が不足し喉の渇きを感じたときには、すでに軽い脱水症になっているため注意が必要です。
具体的な症状
脱水症状の具体的な内容は、「どの程度の脱水症か」で異なります。軽症の場合は、「喉が渇く」「めまい」「食欲減退」「尿量の減少」「大量に汗をかく」などの症状が現れることがほとんど。
症状が中等度の場合は、「皮膚の紅潮化」「全身の脱力感」「手足の震え」「ふらつき」「頭痛」「呼吸困難」などが引き起こされます。
軽症のときとは異なり汗は出ませんが、だからといって脱水症ではないと自己判断しないよう注意しましょう。そして重症の場合は、「失神」「目の前が暗くなる」「筋痙攣」「飲み込むのが困難になる」などの症状が現れます。
子どもや高齢者は、大人にくらべて脱水状態になりやすく、重症化しやすいので、より注意が必要です。
小児の場合
意思疎通ができる子どもであれば水分補給させやすいですが、乳児の場合は嫌がって飲まないこともあるでしょう。子どもの脱水症に早く気づけるよう、具体的な症状も押さえておきましょう。
| 脱水状態 | 体重減少 | 脱水症状 |
|---|---|---|
| 軽症 | 4〜5% | ・皮膚の色が変わり弾力性がなくなる ・大量に汗をかく ・尿量が減少する |
| 中等度 | 6〜9% | ・全身ぐったりした状態になる ・皮膚が蒼白になる ・目が落ちくぼんでいる ・汗の量が減る |
| 重症 | 10%以上 | ・全身が痙攣する ・頭部のくぼみが顕著になる ・汗が出なくなる |
子どもは「水分の喪失量の増加」による脱水症を招きやすいです。とくに乳児の場合、腎臓が未発達のため尿の量が多く、呼気や皮膚から失われる水分量も、大人とくらべると多い傾向にあります。下痢や嘔吐などの症状が出てしまうと、さらに水分量が失われ、脱水症を招きやすくなります。
また、離乳食がはじまる前の乳児だと「母乳とミルクで十分水分はとれているから、水やお茶などを飲ませなくてもよい」といわれることもあり、あえて水を与えないこともあるかもしれません。
しかし、母乳やミルクの量が不十分だと脱水症を引き起こす恐れがあります。とくに汗をかきやすい暑い時期は積極的に水分補給させるほか、オムツの状態をこまめに確認するようにしましょう。
半日以上排尿がなければ、脱水症を引き起こしている可能性があります。脱水症になる前にオムツで尿量をチェックし、「いつもより排尿が少ないかも」と感じたら早めに水分補給をさせることが大切です。
高齢者の場合
高齢者の場合、子どもよりも体内の水分量が少ないため、脱水症に気づきにくく、熱中症などのリスクが高くなるといわれています。小児の場合、体内の水分は70%ですが、65歳以上の高齢者では55%~50%にまで減少するようです。
加齢によって食欲が減退すると、食事からの水分を摂取できないだけでなく、飲み物を口にすることも少なくなります。さらに、夜間のトイレを気にして、水分を控えるご高齢の方も少なくありません。
もちろん「水分の喪失量の増加」も原因ですが、ご高齢の方は、基礎代謝量が減少することによって、代謝によって生成される水分も減少します。また、加齢により筋肉や皮下組織の備蓄水分量が減少するため、病気に関係なく脱水症を引き起こしやすくなっています。
2015年の統計では、熱中症で死亡した人の約8割が65歳以上でした。可能であれば、子どもの場合と同じように、一緒にいる家族や友人がよく観察し、水分補給を促してあげましょう。
脱水症と熱中症の違い
熱中症は、気温や湿度、体調等によって体の中に熱がこもり、体温が上がり続けてしまう状態をいいます。一方脱水症は、体内の水分が少なくなり、汗を出して体温を下げることができなくなっている状態です。
脱水症になっていると、熱中症のリスクは上昇しますが、熱中症の症状が進んだ結果、脱水症になることもあります。熱中症と脱水症は同じものではありませんが、それぞれ関係の深い症状といえるでしょう。
脱水症になりやすいタイミング

脱水症を招きやすいタイミングには、主に「日常生活」「スポーツ時」「夏場・冬場」の3つがあげられます。
日常生活
日常生活の中でもとくに注意したいタイミングが「就寝時」です。私たちは寝ている間も大量の汗をかきます。すると、体内の水分が失われ、脱水症を招く危険性があるのです。
また、「入浴時」も注意したいタイミングのひとつです。就寝時と同じく、入浴時も大量の汗をかくため体内の水分が失われやすく、脱水症を招いてしまうことがあります。
このほか「飲酒後」も脱水症を招きやすいタイミングになるので、注意しなければなりません。なぜなら、アルコールには利尿作用があるからです。
たとえば、ビールを10本飲んだ場合の尿の排出量は、ビール11本分に相当するといわれています。つまり、飲酒後は利尿作用により尿の排出量が多くなってしまうということ。そのため、飲酒後はアルコール以外の飲料で水分補給をしないと、脱水症を招きやすくなります。
スポーツ時
スポーツ時は普段よりも汗をかきやすく、体内の水分が多く失われます。気温が高いときはもちろん、気温の低いときや屋内でのスポーツであっても汗をかきます。水分補給を怠ってしまうと、脱水症を引き起こしやすくなるため注意しておきましょう。
夏場・冬場
夏場・冬場も脱水症を招きやすくなります。夏場は、気温や湿気によって汗をかきやすく、体内の水分が多く失われがちです。そのため、夏場に脱水症を引き起こしてしまう方は少なくありません。
一方で、冬場は「乾燥」が原因で脱水症を引き起こしやすくなります。私たち人間は、汗や尿以外にも皮膚からの水分蒸発によって体内の水分を排出しています。冬場は、乾燥によって「水分蒸発がしやすい状態」になっているので、脱水症を引き起こしやすくなるのです。
さらに、冬場に脱水症を招いてしまう原因には「喉の渇きを感じづらくなってしまうこと」もあげられます。「喉が渇いてから水を飲む」というケースが多くなり、気づかぬうちに脱水症を引き起こしやすい状態を作ってしまうのです。
脱水症というと「夏場に起こるもの」というイメージがあるかもしれませんが、冬場も十分注意しなければなりません。
このほか、冬場に脱水症を招いてしまう原因には「感染症による発熱や嘔吐、下痢」もあげられます。冬場は乾燥により風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどにかかりやすくなります。
これらの感染症にかかった場合、熱が出たら体温が上昇し、汗をかきやすくなるでしょう。また、嘔吐や下痢症状がある場合も、水分が体内から排出され、脱水症を引き起こす可能性があります。
塩分やミネラルの摂取も重要
脱水症の場合、水だけではなく、塩分も失われていますので、適度な塩分も補給しなければなりません。スポーツをしていて大量の汗をかくときは、塩分濃度0.1~0.2%程度の水分補給がすすめられています。スポーツ以外でも、足がつったりしたときは塩分が不足しているのかもしれません。
加えて、ミネラルの摂取も重要です。ミネラルとは、ナトリウムやマグネシウム、カリウムなどの電解質のことで、体内では常に水分とミネラルのバランスを保つ機能が働いています。
ミネラルを含まない水分を大量に摂取してしまうと、体はバランスを保とうと排尿を促すため、せっかくとった水分が無駄になりかねません。こうした理由から、汗をたくさんかくときの水分補給は、塩分やミネラルも同時に補給することがのぞましいでしょう。
かくれ脱水に素早く気づくためのチェックポイント

かくれ脱水とは、気づかぬうちに体内の水分量が減り、脱水症を引き起こす一歩手前の状態のことです。先述したように冬場は、夏場にくらべて喉が渇きにくいうえ、乾燥によって水分が蒸発しやすい状態になり、かくれ脱水になることも珍しくありません。かくれ脱水を放置していると脱水症を引き起こしてしまうため、以下のようなサインがみられたら早めの水分補給を心がけましょう。
- 喉が渇く
- ダイエットをしているわけでもないのに短期間で体重が減っている
- 尿の色がいつもより濃くなっている
- 感染症や病気にかかっているわけでもないのに体温が37℃以上と高くなっている
- 頭がぼーっとする
- 集中力が低下する
- 汗を大量にかく
上記の症状が現れても、「少し体調が悪いのかも」と軽視されがちです。かくれ脱水とは気づかず「休んだら治る」と思い、水分補給もせず寝てしまうこともあり得るでしょう。
水分補給をしないとそのまま脱水症へと進行してしまうため、上記のかくれ脱水のサインを覚えて、ひとつでも該当するときは水分を摂取することをおすすめします。
また、先述したようにご高齢の方は食欲の減退により食事から水分をあまり摂取できなくなるうえ、飲み物を飲むことが少なくなります。
また、夜間にトイレに行く回数を減らすために夜は飲み物をあまり飲まないようにしている方もいるでしょう。ご高齢の方はかくれ脱水を引き起こしやすいので、以下の症状がみられたら早めに水分を摂取することが大切です。
- 口の中が粘つく
- 唾液が少なく、また唾液を飲み込めないときがある
- 皮膚にツヤがなく乾燥している
- ポロポロと皮膚が落ちる
- 便秘になった、もしくは以前にくらべて便秘がひどくなった
- 手の甲の皮膚をつまんで離したあと、跡が3秒以上残ってすぐに元に戻らない
- 足のすねがむくんで靴下の跡が10分以上残ったままになる
かくれ脱水は自身が早めに気づくことが重要です。上記の項目に該当する症状がないか確認し、ひとつでも疑いがあれば喉が渇いていなくても飲み物を飲むようにしましょう。
脱水症の予防に最適!アクアクララのお水で手軽に水分補給
脱水症予防として「おいしい水の確保」「水分補給のしやすさ」にこだわるなら、アクアクララのウォーターサーバーの利用がおすすめです。
ミネラル成分をバランスよく配合したお水
アクアクララで使用しているお水は、カルシウム・ナトリウム・カリウム・マグネシウムの4種のミネラル成分をバランスよく配合した軟水です。
お水の硬度は29.7mg/L。口当たりがまろやかで日本人が「飲みやすい」と感じる仕上がりになっていますので、「おいしい水で水分補給したい」という方には、とくにアクアクララのウォーターサーバーがおすすめです。
天然水ではなくRO膜(逆浸透膜)でろ過した安心安全な軟水 – RO水
温水・冷水でおいしいお水が手軽に味わえる
アクアクララのウォーターサーバーなら、温水・冷水の両方を瞬時に出せます。たとえば、寒い冬の時期には「温かい飲み物を飲みたい」と思うことも少なくありません。やかんや電気ケトル、電気ポットなどでお湯を沸かすとなると、待ち時間が発生しますし手間もかかってしまいます。
アクアクララのウォーターサーバーなら手間なく温水を用意できます。「飲みたい」と思ったときにすぐ飲めて、スムーズな水分補給を行えます。
ウォーターサーバーはなぜお湯が出る?その温度は?仕組みとお湯の使い方
まとめ
脱水症は、誰もが引き起こす可能性のある危険な状態です。とくに、ご高齢の方や幼い子どもは脱水症を招きやすいため、こまめに水分補給を行うことが大切です。また、過ごす環境も脱水症を招く要因になるので、今回ご紹介した予防法を参考にしつつ、水分補給がしやすいよう、ウォーターサーバーの利用も検討してみてください。
アクアクララのウォーターサーバーなら、温水・冷水をすぐに準備できます。おいしいお水が飲めるだけでなく好きな飲み物を手軽に作れるので、脱水症の予防に効果的です。
さらにアクアクララでは、「卓上タイプ」のウォーターサーバーも取り扱っています。卓上タイプならカウンターキッチンや棚の上などの省スペースに設置することができるので、「ウォーターサーバーの置き場所がない」というご家庭でも利用しやすいでしょう。
寝室に置けば、寝る前や寝起きにも水分補給がしやすくなるので、脱水症を防ぐためにもぜひウォーターサーバーの利用を検討してみてはいかがでしょう。
※この記事は正しい情報発信を行うために、医師に監修を依頼しております。商品について医師が推薦を行うものではありません。
監修者
桐田 泰江(麻酔科医)

浜松医科大学医学部卒業後、日本人医師で初めてシドニー大学医学部大学院「痛みマネジメント科」の修士号を取得。麻酔科医として勤務後、2022年にM&K産健を設立。現在は、健診医業務・嘱託産業医業務などを行うほか、健康に関する記事の執筆や監修などにも携わっている。